インフルエンザの予防接種は何歳から受けたほうがいい?
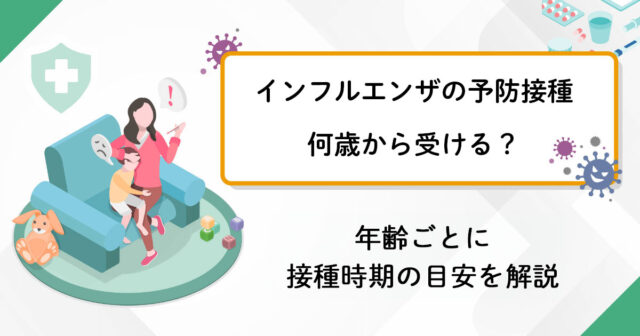
初めての冬を迎える赤ちゃんを育てるママ・パパにとって、予防接種のタイミングは悩ましいポイントのひとつかもしれません。
「生後何か月から接種できるの?」「いつ受けるのがいいの?」といった不安の声も多く聞かれます。
一部のワクチンは生後6か月頃から接種が可能とされており、感染症の流行が始まる前に準備を進めておくことが勧められています。ただし、ワクチン接種の効果や必要な回数・間隔は年齢によって異なるため、医師と相談しながら適切なスケジュールを立てることが大切です。
この記事では、年齢ごとの接種スケジュールの目安や、予防接種に関する基本的な情報を分かりやすくまとめました。これからの季節を安心して迎えるための一助として、予防接種の準備に役立ててください。
- 1942年、神奈川県小田原市で出生
- 鳥取大学医学部卒業
- 順天堂大学医学部附属順天堂病院小児科入局
- 日本小児科医会名誉会長
- 2024年11月旭日双光賞受賞
インフルエンザ予防接種は生後6ヶ月から接種可能
インフルエンザワクチンの接種開始年齢について、厚生労働省の公式ガイドラインでは、生後6ヶ月から接種が可能とされています。
乳幼児期は免疫機能がまだ発達段階にあり、ウイルスなどの感染症に対する抵抗力が十分ではない場合もあります。そのため、インフルエンザなどにかかった際には注意が必要とされており、一部では気管支や肺への影響、まれに神経系の合併症が報告されることもあります。
生後6ヶ月を迎えた時点で接種が可能になるのは、この時期から母体由来の抗体が減少し、自身で免疫を獲得する必要が出てくるためです。特に保育施設に通う予定がある場合や、兄弟と接触する機会が多い家庭では、感染リスクについて早めに医師へ相談することが推奨されます。
6ヶ月未満の赤ちゃんは接種できない理由
新生児期から生後6か月頃までの赤ちゃんは、免疫システムがまだ成熟しておらず、体の防御機能が不安定な時期です。また、妊娠中に母体から胎盤を通じて受け取った「移行抗体」が、感染症に対する一定の防御を担うとされています。
この抗体が体内に存在していることで、ワクチン接種による免疫反応が十分に起きにくいとされるため、現時点では生後6か月未満の乳児への接種は実施されていません。加えて、この年齢層での接種に関する十分なデータが限られていることもあり、安全性や有効性を慎重に評価する必要がある段階といえます。
そのため、この時期の赤ちゃんを感染から守るためには、まわりの大人や兄弟などが感染症予防を意識することが重要です。具体的には、ワクチン接種を検討するほか、手洗いやマスクの着用、換気などの日常的な対策を徹底することが、家庭内での感染リスクを減らすことにつながります。
1歳未満と1歳以降で異なる接種の考え方
インフルエンザワクチンの効果は年齢により大きく異なり、とくに「1歳」をひとつの目安として、接種の効果や目的についての考慮点が変わってきます。
日本小児科学会の資料では、1歳未満の乳児におけるワクチンの有効性については明確な評価が確立されていないとされています。生後6か月から接種は可能ですが、この時期はまだ免疫システムが発達途上であり、ワクチンに対する反応も限られる可能性があると言われています。そのため、感染予防の目的で接種しても、発症を完全に防げるとは限らず、実際に感染してしまうこともあります。
一方で、1歳以降になると免疫の働きが安定してくるため、ワクチンの効果が得られる可能性が高まります。とくに1歳以上6歳未満の子どもにおいては発熱を指標とした有効率は20~30%となり、発熱の発症頻度を一部抑える傾向が報告されているというデータもあり、一定の予防効果が期待できます。
興味深いことに、0歳時にワクチンを接種すると「プライミング効果」により、次シーズン(1歳以降)のワクチン効果が高まることも報告されています。ただし、こうした効果の有無や程度も個人差があるため、お子さんの健康状態や生活環境(保育園通園、きょうだいの有無など)を考慮し、かかりつけ医と相談の上で接種を検討することが重要です。
保育園や兄弟がいる場合の接種判断
保育園や幼稚園などの集団生活環境における感染リスクや、兄弟を通じた家庭内感染の可能性を踏まえると、インフルエンザワクチンの接種についてはそれぞれの家庭ごとに慎重な判断が求められます。
保育園のような施設では、多くの子どもたちが密に接触するため、感染症が広がりやすいとされる環境のひとつです。インフルエンザは主に飛沫感染や接触感染によって拡がるため、こうした場所では感染のリスクが高まります。
また、学校や保育園に通っている兄弟がいる家庭では、ウイルスが家庭内に持ち込まれる可能性もあるため、生後6か月以上の乳児については、接種のタイミングを含めて医師と相談することが大切です。
環境要因を踏まえて接種を検討する際には、以下のような点を医療機関で相談しておくと安心です。
- 保育園や地域での流行状況や、感染の予測傾向
- 兄弟からの感染リスクの有無
- 家族全体での予防接種の計画(いわゆる「間接的な保護効果」への配慮)
とくに、0歳から保育園に通う乳児や、就学児の兄弟がいる0歳児では、周囲の感染状況をもとに、生後6か月以降の接種を医師と相談のうえ検討することが推奨されています。
また、感染の拡大を防ぐという観点からは、乳幼児本人だけでなく、保護者・保育士・教職員など、周囲の大人も含めた感染対策が重要です。日常的な手洗いや消毒、換気のほか、ワクチン接種の有無も含めて、家庭や保育施設で一体となった対応が求められます。
子どもの接種回数と最適な接種時期
お子さんのインフルエンザワクチン接種について、いつ何回受ければよいのでしょうか。子どもの免疫システムは成人とは異なり、最適な予防効果を得るためには適切な接種回数と時期を選ぶことが重要とされています。
年齢や体重ではなく、生後6か月から13歳未満という年齢基準で接種回数が決められており、流行時期を考慮したスケジュール計画も必要です。ここでは子どものインフルエンザ予防接種について、接種回数の根拠と理想的な時期について詳しく解説します。
13歳未満は2回接種が推奨される理由
13歳未満の子どもに対して2回の接種が推奨されている背景には、免疫反応の特徴が関係しています。厚生労働省や日本小児科学会の指針では、生後6か月から12歳(13歳未満)の子どもには2回の接種が推奨されています。
子どもの免疫システムは大人に比べてまだ発達途上のため、1回の接種だけでは十分な免疫が得られにくい場合があります。研究によると、1回の接種よりも2回の接種を受けた場合に抗体価の上昇が認められることが報告されています。ただし、免疫の反応には個人差があり、すべての方に同じようにあてはまるわけではありません。
2回目の接種では、初回接種によって作られた免疫の記憶が強化されます。これにより、インフルエンザウイルスに対する防御がより支えられる可能性が高まります。
なお、1回目の接種時に12歳で、2回目の接種時に13歳になっている場合でも、12歳の年齢区分として2回目の接種を行うことが認められています。
1回目と2回目の接種間隔は2~4週間
13歳未満の子どもに対して、インフルエンザワクチンを2回接種する場合、1回目と2回目の間隔を2~4週間あけることが、厚生労働省の指針で推奨されています。これは、子どもの免疫反応の仕組みに配慮した接種スケジュールです。
1回目の接種では、体内で抗体がつくられ始め、免疫反応が起こります。しかし、この段階ではまだ免疫が十分に整っていません。2回目の接種によって追加の刺激が加わることで、免疫の働きがよりしっかりとサポートされます。
2~4週間という期間は、初回接種後の反応が落ち着き、2回目の接種によって「ブースター効果」が発揮されやすいと考えられているタイミングです。なかでも、4週間程度の間隔をあけた場合に、免疫応答が高まりやすいとする見解もありますが、これにも個人差があります。
接種の間隔が予定より前後してしまった場合でも、医師の判断のもとで体調が安定していれば、2回目を受けることで一定の免疫反応が得られるでしょう。
11月までに接種完了が理想的なスケジュール
インフルエンザの流行時期を踏まえると、11月中に接種を完了しておくスケジュールが適切とされています。日本では例年、12月から翌年4月頃にかけてインフルエンザが流行し、特に1月末から3月上旬にかけて流行のピークを迎える傾向があります。
ワクチン接種後、体内で免疫が働き始めるまでには通常2週間ほどかかるとされており、流行が始まる前に接種を終えておくことで、より早い段階での備えにつながると考えられています。特に13歳未満の子どもは2回接種が推奨されているため、1回目を10月中に済ませ、2~4週間の間隔をあけて11月中に2回目を終えるスケジュールがひとつの目安とされています。
厚生労働省も、12月中旬までに接種を終えることが望ましいとする見解を示しています。とくに流行のピークに備えるには、11月末までに完了しておくことで、接種のタイミングとしては適切とされることが多いようです。
インフルエンザ流行時期から逆算した計画
インフルエンザワクチンの接種スケジュールを立てる際には、地域ごとの流行傾向や年ごとのパターンを考慮することが大切です。国立感染症研究所によると、日本におけるインフルエンザの流行は、例年11月下旬から12月上旬頃に始まり、翌年1月から3月頃にかけて患者数が増える傾向があります。
このような流行パターンを踏まえると、2回接種が推奨される13歳未満の子どもの場合、1回目を10月中旬〜下旬に行い、2〜4週間あけて11月中旬〜下旬に2回目を終えることで、12月の流行開始時期に備えやすくなるとされています。ただし、年によっては流行が早まるケースも報告されており、10月初旬から接種を開始するケースも見られます。
また、地域によって流行開始のタイミングには差があるため、お住まいの自治体や医療機関、保健所などから提供される最新の流行予測や接種情報を参考にすることが重要です。
万が一、計画通りに接種できなかった場合でも、医師の判断のもとで、できる限り12月末までに2回目の接種を終えておくことで、一定の備えになる可能性があります。
年齢別の接種量と接種方法
インフルエンザワクチンの接種量は、年齢や体格、免疫の発達段階に応じて異なります。一般的には、乳幼児には0.25ml、年長児や成人には0.5mlが使用されます。
これは安全性と免疫応答のバランスを考慮して設定されており、厚生労働省の指針などに基づいています。年齢の境界にあたる場合は、医師が体調や接種歴などをもとに適切な接種量を判断します。
それぞれの年齢層における接種量設定の根拠について、詳しく見ていきましょう。
6ヶ月~3歳未満は1回0.25mlを2回接種
生後6ヶ月から3歳未満の乳幼児には、インフルエンザワクチンを1回0.25ml、2〜4週間の間隔をあけて2回接種することが推奨されています。この接種量は、乳幼児期の免疫機能の発達段階と体格に配慮して設定されており、安全性と免疫応答の両面から検討されています。
6ヶ月未満の乳児にはインフルエンザワクチンは接種できないため、生後6ヶ月を過ぎた時点で速やかに接種を開始することが重要です。この時期の子どもは免疫が未発達であり、インフルエンザにかかると重症化するリスクがあることも指摘されています。
0.25mlという少量での接種は、乳幼児の身体への負担を抑えながら、必要な免疫刺激を与えることを目的とした設定です。2回の接種によって、1回だけでは得られにくい免疫応答を補うことができます。
3歳~13歳未満は1回0.5mlを2回接種
3歳から13歳未満の子どもには、1回0.5mlのインフルエンザワクチンを2~4週間の間隔をあけて2回接種することが一般的とされています。この年齢では、免疫システムが乳幼児期より成熟しているため、接種量を増やすことで適切な免疫反応を得やすくなると考えられています。体格の成長に伴い、必要とされるワクチン量も増えるためです。
また、幼児から学童期にかけては集団生活の機会が増え、感染のリスクが高まる時期でもあります。6歳未満の子どもでは2回接種により一定の有効性が示されているほか、B型インフルエンザに関しては2回接種が推奨される場合もあります。
接種後には、発熱や注射部位の反応などが起こることがあるため、保護者には事前に健康観察の重要性について説明があります。なお、1回目の接種時に12歳で、2回目の接種時に13歳となった場合も、12歳として2回目を接種することが一般的です。
13歳以上は1回0.5mlで接種完了
13歳以上では、1回0.5mlの接種で免疫獲得が完了するとされており、原則として1回接種で十分な効果が期待できます。この年齢では免疫システムが成熟し、成人と同様の免疫反応を示すとされています。過去の感染経験により一定の抗体があることも影響し、1回接種で十分な免疫が期待できる場合が多いです。
ワクチンの添付文書には「13歳以上は1回または2回接種」と記載されていますが、医師が必要と判断した場合は2回接種が行われることもあります。特に免疫機能が低下している方などは、この例にあたります。
また、13歳以降も毎年の接種を続けることで、成人期のインフルエンザ予防効果を維持しやすくなります。65歳以上の定期接種対象者も、原則として1回の接種で実施されています。
接種前に確認すべき注意点
インフルエンザワクチンを接種する際は、お子さんの安全のためにいくつかのポイントを確認することが大切です。
接種は体調が良好なときに行うのが基本です。接種当日の体調はもちろん、過去のアレルギーの有無や現在服用している薬の情報も正確に把握しておきましょう。
また、他のワクチンとの接種間隔を守ることも重要です。医師と事前に相談することで、適切な接種時期や副反応のリスクについて確認し、安全に予防接種を受ける準備が整います。
発熱や体調不良時は接種を延期する
明らかな発熱(37.5℃以上)がある場合、インフルエンザワクチンの接種はできません。これは予防接種実施規則に基づくもので、医師はその状況をふまえて接種不適当と判断します。
また、37.5℃未満でも、お子さんの普段の体調や平熱を考慮して、接種の適否を判断することが重要です。風邪の症状やいつもより元気がない場合には、接種を見合わせることが望ましいとされています。
体調がすぐれないときに接種を延期することで、ワクチンの効果をより発揮しやすく、副反応のリスクも抑えられます。接種を延期した場合は、体調回復後に医療機関に相談し、適切な時期に改めて接種を受けることが大切です。
流行シーズン前の12月中旬までには接種を完了することが望ましいとされています。
他のワクチンとの接種間隔について
インフルエンザワクチンは不活化ワクチンに分類されるため、他の多くのワクチンとの接種間隔に特別な制限はありません。令和2年10月1日以降、注射用生ワクチン同士を除き、異なる種類のワクチンの接種間隔の制限が撤廃されています。
新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時に接種することが可能で、接種間隔の制限も設けられていません。一方で、新型コロナワクチン以外のワクチンと組み合わせる場合には、原則として2週間以上の間隔をあけることが推奨されています。
同時接種を行う際は、医師が必要と判断した場合に限られます。複数のワクチンを混ぜて1本の注射器で接種することは認められておらず、接種部位は少なくとも2.5cm以上離して別々に行います。
ワクチン接種のスケジュールは医師と相談しながら、確実に免疫を得られるように計画することが大切です。
卵アレルギーがある子どもは必ず医師に相談
インフルエンザワクチンは鶏卵を用いて製造されるため、微量の卵成分(オボアルブミン)が含まれています。国内で製造されるワクチン1回分に含まれる卵成分は1~10ナノグラムと非常に少なく、海外製品よりも少ないとされています。そのため卵アレルギーがある場合でも、多くのお子さまは問題なく接種が可能です。
ただ、インフルエンザワクチンの添付文書には、鶏肉や卵などにアレルギーがある方を「接種要注意者」に含めているため、軽度のアレルギーであっても接種は慎重に行われます。
過去に卵摂取でアナフィラキシーなどの重篤な症状を経験したことがある場合や、インフルエンザワクチンでアレルギー反応があった場合は、接種前に必ず専門の医師に相談することが大切です。血液検査の結果だけでなく、実際の症状や反応についても正確に伝えましょう。
