インフルエンザ予防接種の効果一覧!年齢別・症状別に見る予防力の違い
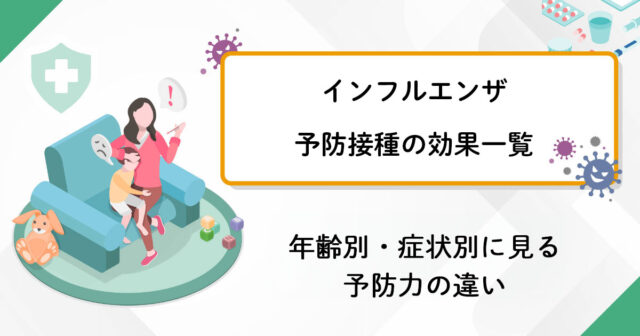
インフルエンザの季節が近づくと、予防接種を受けるかどうか迷う方は多いでしょう。特に、家族の中に乳幼児や高齢者、持病のある方がいる場合はなおさらです。年齢や健康状態によってワクチンによる予防の程度が変わるからです。
この記事では、乳幼児・小児・成人・高齢者のそれぞれの年齢層で、インフルエンザワクチンがどのような効果を持つ可能性があるか、また、基礎疾患(持病)がある場合の予防力について解説します。ご家族に最適な予防接種の判断材料として、ぜひお役立てください。
- 1942年、神奈川県小田原市で出生
- 鳥取大学医学部卒業
- 順天堂大学医学部附属順天堂病院小児科入局
- 日本小児科医会名誉会長
- 2024年11月旭日双光賞受賞
インフルエンザ予防接種の発症予防効果と有効率
インフルエンザワクチンには、インフルエンザの発症を一定程度抑える効果が期待されています。ただし、感染を完全に防ぐものではありません。
ワクチンの効果を示す指標として「有効率」が用いられており、科学的な研究をもとに評価されています。例えば、国内の研究では、6歳未満の小児を対象にした調査で発症予防に対する有効率が約60%と報告されています。
参照元:インフルエンザQ&A:Q.21: ワクチンの効果、有効性について教えてください。|厚生労働省
ただし、インフルエンザワクチンの予防効果は、ウイルスの種類や流行している株とワクチンの適合性、接種時期など複数の要因によって変わることがあります。麻疹や風疹のワクチンと比べると、発症予防効果はやや低いとされています。
年齢別の発症予防効果データ
年齢によってインフルエンザワクチンの発症予防効果には違いがあることが、複数の研究で明らかになっています。
乳幼児については、報告によって多少幅がありますが、概ね20〜60%の発症予防効果があったと報告されています。特に、初回接種後に2回目の接種を行うことで、より予防効果が期待できるとされています。
参照元:インフルエンザQ&A:Q.23: 乳幼児におけるインフルエンザワクチンの有効性について教えて下さい。|厚生労働省
成人では年代によって効果に差が見られます。海外の研究では、以下のように発症予防効果が報告されています。
- 小児(2〜17歳):63〜65%
- 成人(18〜64歳)36〜55%
- 65歳以上の成人:40〜55%
高齢者に関する国内の調査では、65歳以上の高齢者福祉施設に入所している方で34〜55%の発症を抑える効果が示された例もあります。年齢が上がると免疫の反応が弱くなるため、若年者と比べると効果が限定的となる場合があります。
予防接種における「有効率」の意味と考え方
「有効率60%」と聞くと「ワクチンを接種した人の60%がインフルエンザにかからない」と思われがちですが、実際の意味は異なります。
「有効率」とは、ワクチンを接種しなかった場合の発症リスクと比べて、接種によってどれだけそのリスクが相対的に下がったかを示す指標です。個人に対する効果ではなく、集団全体におけるリスク低減の割合を数値化したものです。
たとえば、ある集団でワクチンを接種しなかった100人のうち30人がインフルエンザを発症した場合(発症率30%)、一方で、ワクチンを接種した200人のうち24人が発症したとすると(発症率12%)、このケースの有効率は次のように算出されます。
この計算結果は、「ワクチンを接種しなかった場合と比べて、接種した場合には発症リスクが60%低下した」と解釈されます。つまり、全員が確実にかからなくなるという意味ではありません。
有効率はあくまで集団指標です。ワクチンの効果には、年齢・健康状態・接種時期・流行しているウイルス株との一致度など、さまざまな要因が関わっており、個人差もあります。
また、接種によって「重症化のリスクが下がる可能性がある」とされることもありますが、これも一人ひとりに同じようにあてはまるわけではありません。
インフルエンザワクチンの重症化予防効果
インフルエンザワクチンの主な目的は、感染そのものを防ぐことよりも重症化のリスクを低減することにあります。ワクチン接種により、肺炎や脳症などの重篤な合併症を防ぎ、入院や死亡のリスクを大幅に減少させることが医学的に証明されているのです。
では、具体的にどの程度の重症化予防効果があるのでしょうか。年齢や基礎疾患の有無によって、その効果に違いはあるのでしょうか。医学的根拠に基づいて解説していきます。
死亡率や入院リスクの減少データ
インフルエンザワクチンによる重症化リスク低減については、国内外でさまざまな研究が行われています。
国内の研究によると、65歳以上の高齢者福祉施設に入所している高齢者に対するワクチン接種では、82%の死亡を阻止する効果があったとされています。これは厚生労働科学研究費補助金による大規模な研究結果で、インフルエンザによる死亡リスクを大幅に削減できることを示しています。
また、海外の複数の研究を統合したメタ解析では、以下のような傾向が示されています。
- 18歳から65歳の成人では、インフルエンザ関連の入院リスクが約51%低下した傾向がある
- 65歳以上の高齢者においては、重症化リスクが約37%軽減される傾向がみられた
これらはあくまでも集団における統計的な傾向であり、すべての人に当てはまるわけではありません。
他にも、65歳以上の高齢者のインフルエンザワクチン接種後に、以下のような入院リスクの低下傾向が見られたという報告があります。
- 呼吸器合併症:12〜26%低下
- 心血管合併症:39〜47%低下
- 急性腎障害:23%低下
参照元:https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-025-03955-w
これらのデータは、医療機関への負担軽減や公衆衛生の観点からも注目されていますが、やはり個々の症例により異なる結果となる可能性があるため、ワクチン接種の効果には個人差があることを念頭に置いておくことが重要です。
重症化しやすい方への接種の重要性
インフルエンザワクチンは、特に重症化リスクの高い方々にとって生命を守る重要な手段となります。高齢者、基礎疾患保有者、妊婦などは、インフルエンザにかかると合併症を引き起こしやすく、場合によっては死に至る可能性もあるのです。
重症化リスクが高いとされるのは、一般的に以下のような方々です。
- 65歳以上の高齢者
- 心疾患、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、喘息、慢性腎疾患、脳血管疾患などの基礎疾患を持っている方
- 免疫機能が低下している方(例:がん治療中、免疫抑制剤を使用中など)
- 妊娠中の方
これらの方々では、ウイルスに対する免疫反応が弱くなることがあり、重篤な合併症を併発するリスクが高まります。
高齢者では免疫機能の低下により、続発性細菌性肺炎のリスクが特に高くなります。小児はインフルエンザ関連脳症の発生率が成人よりも高く、解熱剤の不適切な使用によるライ症候群にも注意が必要です。基礎疾患を持つ方では、インフルエンザをきっかけとして既存の疾患が悪化し、入院治療が必要となるケースが多く見られます。
予防接種法では、重症化予防効果による便益が大きいと考えられる65歳以上の方、および60〜64歳で心臓・腎臓・呼吸器機能に重度の障害がある方、HIV感染による免疫機能障害のある方を定期接種の対象としています。これらの方々には、毎年のワクチン接種が強く推奨されているのです。
インフルエンザ予防接種の効果持続期間と免疫獲得時期
インフルエンザワクチンを接種してから、いつ頃から効果が現れ、どの程度持続するのでしょうか。適切な接種時期を決めるために、免疫獲得の時間経過と効果の持続性についての基本的な知識を知っておくことが役立ちます。
ワクチンによる免疫反応は、接種後すぐに最大となるわけではなく、体内で徐々に進行していきます。そのため、インフルエンザの流行に備えるには、計画的な接種が重要とされています。
接種後の免疫獲得までの期間
インフルエンザワクチンを接種してから、体内で免疫が形成されるまでには一定の時間がかかります。接種後、免疫システムがワクチンの成分に反応して抗体を作り始め、段階的に防御機能が高まっていくとされています。
一般的に、接種からおおよそ2週間ほどで体内の抗体が増加し始め、1ヶ月程度で抗体量が最も高くなると考えられています。接種してから最初の2週間は十分な効果が発揮できない可能性があるため、流行期よりも早めの接種が推奨される理由がここにあります。
重要なのは、接種直後から効果が得られるわけではないという点です。流行が始まってからワクチンを接種しても、免疫が十分に構築される前に感染してしまう可能性があります。そのため、流行の1ヶ月前には接種を完了しておくことが望ましいとされています。
ワクチン効果の持続期間と変化
インフルエンザワクチンによって得られる免疫は、永久的なものではなく、時間の経過とともに低下していきます。しかし、現在では従来考えられていたよりも長期間にわたって効果が維持されることが明らかになっています。
一般的にインフルエンザワクチンの有効期間は5~6ヶ月程度とされており、1970年代から80年代にかけて言われていた「3ヶ月程度」という説は現在では否定されています。海外の臨床試験では接種後6ヶ月まで観察期間を設定しており、この期間中はワクチンの有効性が保たれることが確認されています。
抗体価の変化パターンを詳しく見ると、接種後1ヶ月でピークを迎えた後、3~4ヶ月かけて徐々に減少していきます。2回接種の場合、1ヶ月後77%、3ヶ月後78.8%の効果が認められますが、5ヶ月後には50.8%まで低下するというデータがあります。
興味深いのは「ナチュラルブースト効果」という現象です。ワクチン接種後にインフルエンザ流行期に入ると、日常生活でウイルスに接触する機会が増え、これが追加接種のような効果をもたらし、免疫力が維持されるのです。
この機序により、流行期間中(11月~3月)は継続的な予防効果が期待できると考えられています。
最適な接種時期として、日本では12月中旬までにワクチン接種を終えることが推奨されています。これは例年1月末~3月上旬に流行のピークを迎えることを考慮したタイミングです。
