インフルエンザ予防接種したのに高熱が出る理由と対処法
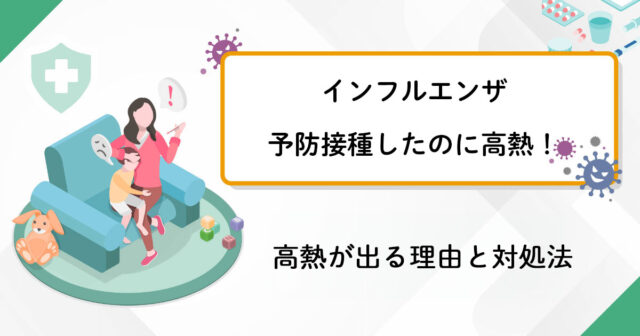
予防接種を受けたあとに高熱が出ると、不安になる方も少なくありません。
「ワクチンが効いていないのでは?」「何か異常があるのでは?」と心配になる気持ちはごく自然なものです。
しかし、予防接種後に発熱が見られることは、いくつかの医学的な要因で説明されています。例えば、副反応として一時的な熱が生じる場合や、接種のタイミングとウイルス感染の時期が重なるケース、個人の免疫反応の違いなどが影響することがあります。
本記事では、予防接種後に発熱が起こる主な要因を紹介し、高熱が出た際の一般的な対応方法について説明します。あわせて、医療機関の受診が推奨される症状の一例も掲載しています。
事前に正確な情報を知っておくことで、体調の変化に対して冷静に対応しやすくなります。予防接種後の体調管理の参考としてご活用ください。
- 1942年、神奈川県小田原市で出生
- 鳥取大学医学部卒業
- 順天堂大学医学部附属順天堂病院小児科入局
- 日本小児科医会名誉会長
- 2024年11月旭日双光賞受賞
予防接種後にインフルエンザで高熱が出る理由
インフルエンザワクチンを接種したにもかかわらず、高熱を伴うインフルエンザにかかることがあります。このような状況が起こる背景には、ワクチンの性質や作用の範囲に関する科学的な理解が関係しています。
ワクチンは感染を完全に防ぐものではなく、発病予防と重症化予防という2つの役割を担っているのです。今回は、なぜ接種後でも感染が起こりうるのか、その医学的メカニズムを詳しく解説していきます。
ワクチンは感染を完全に防ぐものではない
インフルエンザワクチンの基本的な仕組みを知ることで、なぜ感染そのものを完全に防ぐことが難しいとされるのかが理解しやすくなります。
インフルエンザウイルスは、口や鼻、目の粘膜などから体内に侵入し、細胞内で増殖を始めます。現在使用されているインフルエンザワクチンは、この感染の初期段階を物理的に防ぐ働きを持ちません。
接種によって産生される抗体は、ウイルスの増殖を抑えることで症状の進行を抑える効果がありますが、その反応には個人差があります。また、ウイルスの型やワクチン株との一致度合いなどによっても、免疫応答の程度に違いが出ることがあります。
例えば、理化学研究所が行った研究では、不活化ワクチンではワクチン株に対応した抗体が主に産生されると報告されています。一方で、構造が異なるウイルス株に対しては、広く対応できる中和抗体の産生は限定的である可能性が示唆されています。
参照元:ワクチンと感染では作られる抗体の質が異なることを発見|理化学研究所
抗体産生には個人差があり、接種後の免疫反応の強さも人によって異なります。さらに、高齢者や免疫機能が低下している方では、十分な抗体が産生されにくい場合があり、こうした要因が感染や発症のリスクに影響を及ぼす要因となります。
発病予防効果が限定的な背景
インフルエンザワクチンによる発病の予防効果は、流行するウイルスの型や接種対象者の年齢、体調などによって大きく変動します。
国内の研究データによると、65歳以上の高齢者福祉施設入所者では34~55%の発病阻止効果、6歳未満の小児では60%の発病防止効果が報告されています。
高齢者や基礎疾患を持つ方では、免疫システムの働きが若年者と比較して低下しているため、ワクチン接種後の抗体産生が不十分になることがあります。2023年から2024年シーズンのイギリスでの研究では、18~64歳の成人で36~55%、65歳以上の成人で40~55%の有効性にとどまっています。
発病予防における効果には限界があるとされる一方で、ワクチン接種には重症化リスクの低下といった重要な役割があるとされています。
厚生労働省のデータでは、高齢者において82%の死亡阻止効果が確認されており、ICU入室リスクの26%減少、死亡リスクの31%減少といった重要な効果が認められています。
発病を完全に防ぐわけではないものの、死亡に至るような重篤な症状の発生を減らす可能性があることから、接種の意義は非常に大きいのです。
ウイルス型の違いによる影響
インフルエンザワクチンの効果に最も大きく影響するのが、ワクチン株と実際の流行株の一致度です。インフルエンザウイルスはA型(H1N1とH3N2)とB型(山形系統とビクトリア系統)の4価ワクチンが製造されており、WHO(世界保健機関)が毎年の流行予測に基づいて推奨株を選定し、各国でワクチンに組み込まれます。
なかでもH3N2型は、遺伝的な変異が特に早く進むため、予測が難しく、ワクチン株と流行株が一致しない年も少なくありません。この不一致が生じると、ワクチンの感染予防効果が大きく低下し、重症化や合併症のリスクを下げる効果にとどまる場合があります。
さらに、H3N2型は交叉免疫の効果が限定的で、一度感染したり、過去にワクチンを接種したとしても、異なる株には十分な免疫が働かないことが多く見られます。そのため、毎年のワクチン接種が重要になります。
ワクチンの効果を最大限に引き出すには、その年の流行株に近い型が含まれていることが前提となるため、定期的なウイルス監視と迅速なワクチン製造体制が不可欠です。特に高齢者や基礎疾患を持つ方は、H3N2型に感染した場合の重症化リスクが高いため、流行状況にかかわらず、毎年の接種が強く推奨されています。
このように、H3N2型インフルエンザの性質とワクチンの適合性が、シーズンごとのワクチン効果に大きな影響を及ぼしているのです。
参照元:インフルエンザワクチン(季節性)|厚生労働省 / Interim 2023/2024 Season Influenza Vaccine Effectiveness in Primary and Secondary Care in the United Kingdom|PubMed Central
副反応かインフルエンザかの見分け方
インフルエンザワクチン接種後に発熱が見られた場合、それがインフルエンザワクチンの副反応による一時的な発熱なのか、あるいは実際のインフルエンザ感染によるものなのかを判断することは簡単ではありません。どちらも発熱を伴うため、症状だけで区別するのが難しいこともあります。
ただし、発熱の現れ方や持続時間、発症までのタイミングといった点に注目することで、それぞれの可能性を検討する手がかりになることがあります。
症状の経過や体調の変化を注意深く観察し、必要に応じて医療機関に相談することで、適切な対応がとりやすくなります。では各症状の違いを詳しく見ていきましょう。
ワクチン副反応による発熱の特徴
インフルエンザワクチンの副反応による発熱は、接種を受けた方の5~10%に起こります。この発熱は免疫を得る過程で起こる反応で、接種後にみられる代表的な副反応のひとつです。
副反応による発熱は、比較的軽度であることが多く、38℃前後まで体温が上がるケースがよく見られます。また、頭痛や悪寒、だるさなどの症状を伴うこともありますが、これらは通常、接種後2〜3日以内におさまります。
インフルエンザ感染時にみられるような、関節痛や筋肉痛などの強い全身症状は、副反応による発熱ではあまり顕著ではない傾向があります。症状が軽く、安定して経過することが多いとされています。
水分補給や安静など、無理をせず体を休めることで、時間の経過とともに回復する場合が一般的です。ただし、症状が長引く、または悪化するような場合は、医療機関への相談が推奨されます。
インフルエンザ感染による症状の違い
インフルエンザに感染した場合、38℃以上の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感などの全身症状が、比較的急速に現れるのが特徴です。こうした症状は一般的な風邪よりも強く、突然発症するケースが多いとされています。
また、発熱と同時に頭痛が生じ、全身の関節や筋肉の痛み、体を動かすのがつらく感じられることもあります。あわせて、のどの痛み、鼻水、咳などの上気道症状がみられることもあり、複数の症状が同時に現れる傾向があります。発症後の経過については、一般的に7日程度で症状が落ち着いてきます。
高齢の方や基礎疾患を抱える方は、インフルエンザにより重症化するリスクが高まることがあるため、発熱が続く、症状が強い、体調が著しく悪化していると感じる場合には、早めに医療機関へ相談しましょう。
発熱のタイミングと持続期間
ワクチン副反応による発熱とインフルエンザ感染による発熱では、発現時期に明確な違いがあります。ワクチンの副反応による発熱は、多くの場合、接種から24時間以内に見られ、2〜3日ほどで自然におさまることが一般的です。
一方、インフルエンザ感染による発熱は、ウイルスが体内に入ってから1〜3日程度の潜伏期間を経て発症することが多いとされています。このように、症状が出るまでに一定の時間差があることは、判断の手がかりのひとつといえるでしょう。
また、発熱が続く期間にも違いが見られます。副反応による発熱は短期間で改善するケースが多いのに対し、インフルエンザ感染では、発症後5日程度続くことがあり、解熱後も倦怠感や咳などの症状が2〜3日残る場合があります。
発熱のタイミング、持続期間、併発する症状の有無や強さなどを観察することで、状態の把握や適切な判断が可能になります。
予防接種後の高熱への対処法
予防接種後に高熱が発生した場合、適切な対処を行うことで症状の軽減と早期回復を図ることができます。多くの場合、発熱は副反応の一つであり、体が免疫を獲得している証拠でもありますが、正しい対応方法を知っておくことが重要です。
家庭でできる初期対応から医療機関への受診判断まで、段階的な対処法を学び、安全で効果的な症状管理を行いましょう。予防接種後の体調変化に備えて、事前に対処法を知っておくことで、落ち着いて対応しやすくなります。
まず確認すべき症状のチェックポイント
予防接種後に高熱が見られた場合は、体温だけでなく、全身の状態を総合的に確認することが重要です。特に、小さな子供の場合は、体調の変化を言葉で伝えることが難しいため、まわりの大人が丁寧に観察する必要があります。
まずは、意識がはっきりしているかを確認しましょう。呼びかけに反応があるか、表情が普段通りか、目に力があるかなどが一つの目安となります。乳幼児であれば、大きな声で泣けているか、泣き方に違和感がないかといった点も観察ポイントです。
次に、水分や食事の摂取状況をチェックします。乳幼児であれば、母乳やミルクが飲めているか、普段と同じくらいの量を摂取できているかを記録しておくとよいでしょう。嘔吐が続いていないか、尿の回数が極端に少なくなっていないかといった情報も、脱水の兆候を把握する上で参考になります。
体温は腋の下で測定し、1日数回の記録をつけておくと経過を把握しやすくなります。また、手足の温かさにも注目しましょう。手足が温かい場合は、熱を逃がしやすいよう軽めの衣類に調整することがあります。一方で、手足が冷たく感じられる場合は、身体を冷やしすぎないよう注意が必要です。
こうした日々の観察を時系列で記録しておくことで、医療機関を受診した際に医師へ正確な情報を伝える助けになります。
解熱剤の使用と水分補給の方法
予防接種後に高熱が続く場合、必要に応じて解熱剤を使用するケースがありますが、使用にあたってはいくつかの注意点があります。
まず、生後3か月未満の乳児には、原則として解熱剤は使用しません。生後3か月以上の乳児・小児では、医師の判断に基づき、処方されたアセトアミノフェン製剤を用法・用量を守って使用することがあります。
なお、アスピリンや、ジクロフェナク、メフェナム酸などは、インフルエンザ脳症やライ症候群のリスクがあるため、乳児・小児への使用は禁忌とされています。
解熱剤使用のタイミングについては、発熱そのものよりも、以下の状態が見られる場合とされています。
- 発熱によって本人がつらそうにしている
- 睡眠がとれない
- 食事・水分が取れない
体温だけを基準にした予防的な使用は一般的には勧められていません。薬剤使用後も継続的な観察を行い、効果や副作用の有無を確認してください。
一方で、水分補給も重要な対処法のひとつです。高熱により体内の水分が失われやすくなるため、少量ずつこまめに水分を与えることが勧められています。飲みたがらない場合には、アイスクリームやゼリーなどを活用し、水分を摂取しやすい工夫をすることも一つの方法です。
また、室温は22〜26℃程度を目安に調整し、衣類は熱がこもらないような軽装にするなど、周囲の環境も考慮しながら、無理のない範囲で体調を整えていくことが大切です。
医療機関への受診が必要な症状
予防接種後に高熱が出た際には、体調の変化をよく観察し、必要に応じて医療機関に相談することが大切です。中には、緊急性の高い症状もあるため、早期の対応が求められるケースがあります。
特に注意が必要とされる症状には、以下のようなものがあります。
- 呼びかけに反応が鈍い、意識がぼんやりしている
- 顔色が悪く、明らかにぐったりしている
- 嘔吐が繰り返され、水分が摂れない状態が続いている
このような状態が見られる場合、時間帯を問わず、すみやかに医療機関に連絡を取り、状況に応じて救急対応を検討することが勧められます。
また、生後3か月未満の乳児が発熱した場合は、一般的に重大な感染症の可能性も否定できないため、接種後であっても医療機関への受診が推奨されています。
一方、以下のような症状については、緊急性は低いとされるものの、注意深い観察と日中の受診が望まれる場合があります。
- 発熱が24時間以上続いている
- 水分や食事がうまく取れていない状態が続いている
- 機嫌が普段と大きく異なり、長時間不機嫌な様子が続く
これらの場合は、かかりつけ医や地域の医療機関での相談が選択肢のひとつです。ただし、状況によっては判断が難しいこともあります。そのようなときは、各自治体が提供している救急安心センター事業(#7119)や小児救急相談窓口(#8000など)を活用し、医療従事者のアドバイスを受けるのも一つの方法です。
受診時には、次のような情報を整理して伝えると、診察がスムーズになります。
- 接種したワクチンの種類と接種日
- 発熱が始まった時間と体温の変化
- 観察された症状(水分摂取状況、睡眠の様子など)
- お薬手帳や予防接種記録
医師に正確な情報を提供することで、より適切な診察や対応につながります。日頃から記録を残しておくと安心です。
救急安心センター事業:#7119
地域別一般ダイヤル回線はこちらから:救急車の適時・適切な利用(適正利用)|総務省消防庁
子ども医療でんわ相談:#8000
地域別一般ダイヤル回線はこちらから:小児救急相談窓口|厚生労働省
今後の感染予防と注意点
ワクチン接種は感染症に対する予防の一手段ですが、それだけで感染を完全に防げるわけではありません。接種後も、日常生活の中で継続的に基本的な対策を行うことが推奨されています。
効果的な感染予防には、マスク着用や手洗いといった基本対策に加え、日常的な体調管理と計画的なワクチン接種の継続が必要です。これらの対策を組み合わせることで、自分と周囲の人々を守ることができるでしょう。
ワクチン接種後も必要な感染対策
ワクチンを接種した後も、引き続き基本的な感染対策を継続することが大切です。例えば、人が多く集まる場所でのマスクの着用、石けんを使った丁寧な手洗いやアルコール消毒、定期的な換気などが、日常生活で取り入れやすい予防行動の一例です。
インフルエンザワクチンを接種しても、感染する可能性が完全にゼロになるわけではありません。接種後に体内で免疫がつくまでにおよそ1〜2週間が必要とされており、また、発症のしにくさや重症化しにくさには個人差があります。さらに、免疫の効果が持続する期間にも限りがあるとされており、季節ごとに医師と相談しながら適切なタイミングで接種を検討することが大切です。
家庭内や職場などでの感染拡大を防ぐためにも、日頃からの体調管理は欠かせません。発熱や喉の痛みなど、体調に異変を感じた際は、早めの対応と適切な行動制限が推奨されています。無理をせず、休養を取ることも感染対策の一環です。
体調管理で気をつけるポイント
日々の体調管理は、感染症のリスクを下げるうえで大切な要素のひとつとされています。特に、十分な睡眠や適度な運動、栄養バランスの整った食事など、生活習慣を整えることが、免疫機能を良好に保つために役立ちます。
十分な睡眠は免疫機能を正常に保つために欠かせません。睡眠時間が短い人は風邪をひきやすい傾向があるという研究もあり、一般的には6〜8時間程度の睡眠が目安とされています。ただし、必要な睡眠時間には個人差があるため、自分に合った睡眠リズムを見つけることが大切です。
栄養面では、毎日の食事からタンパク質やビタミン、ミネラル、食物繊維などをバランスよく摂取することが推奨されています。偏った食生活や過度な食事制限は体調を崩す要因にもなりかねません。
さらに、適度な運動やストレスとの向き合い方も、体調維持において無視できないポイントです。過度な運動やストレスは体に負担をかける可能性があるため、無理のない範囲で取り入れるようにしましょう。
そして、体調に変化を感じたときには、早めに休息を取り、必要であれば医療機関を受診するなど、柔軟に対応することが大切です。
次回の予防接種に向けた準備
インフルエンザワクチンは、その効果が時間の経過とともに徐々に弱まることが知られています。このため、季節性インフルエンザの流行時期に合わせて、年に1回の定期的な接種を検討することが望ましいとされています。
また、インフルエンザウイルスは毎年流行する型が変化しやすいため、ワクチンもその年の流行株に合わせて改良されます。こうした背景から、その年ごとの流行株に対応した追加接種を行うことで、感染や重症化のリスクを抑えられる可能性が上がります。
今回の接種経験をもとに、次年度の接種計画を立てる際は、医師との相談を通じて、個人の健康状態に応じた判断を行うことが重要です。特に、基礎疾患の有無、年齢、前回接種時の副反応の有無などをふまえて、医療的な観点からのアドバイスを受けることが勧められています。
予防接種法に基づく定期接種対象者は以下の通りです。
- 65歳以上の方
- 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器などの機能に重い障害がある方
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を持つ方(身体障害者手帳1級程度)
この定期接種は、原則として毎年秋から冬にかけて行われています。
参照元:季節性インフルエンザワクチン接種時期ご協力のお願い|厚生労働省
インフルエンザウイルスは毎年異なる型が流行する傾向があるため、その年の流行に対応したワクチンを継続して接種することで、感染や重症化のリスクを下げることができるでしょう。
