インフルエンザの予防接種は医療費控除の対象になる?
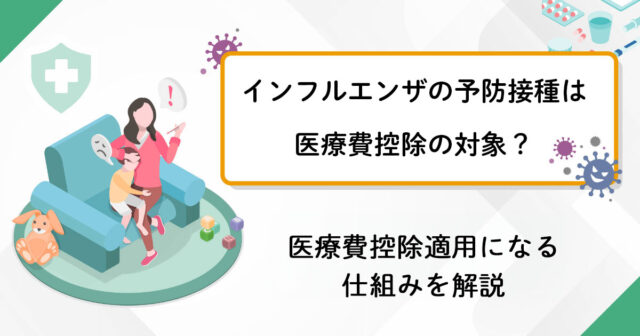
健康な人の予防目的接種と、病気治療中の患者への接種では税務上の扱いが大きく異なります。
インフルエンザ予防接種は、一般的には健康維持や感染予防を目的としたものであるため、原則として医療費控除の対象外とされています。ただし、医師の治療の一環として接種した場合は例外的に控除を受けられます。
制度の基本を理解しておくことで、控除対象外の費用について誤って申告するリスクを減らすことができます。また、控除の対象となるケースを正しく把握しておくことで、必要な手続きを見逃さずに済むでしょう。
確定申告や年末調整の前には、医療費控除の対象範囲を一度整理しておくと安心です。制度の正確なルールを把握しておくことで、不要な手続きや申告ミスを防ぐことにつながります。
- 1942年、神奈川県小田原市で出生
- 鳥取大学医学部卒業
- 順天堂大学医学部附属順天堂病院小児科入局
- 日本小児科医会名誉会長
- 2024年11月旭日双光賞受賞
インフルエンザ予防接種の医療費控除適用について
インフルエンザの予防接種費用が医療費控除の対象になるのかどうか、毎年インフルエンザの時期になると気になる方も多いのではないでしょうか。
多くの方が抱くこの疑問について、税法上の取り扱いを解説します。
予防接種費用が通常の医療費控除対象外とされる理由
医療費控除の対象となるのは「治療または療養に必要な費用」に限定されています。国税庁の見解では、予防接種は疾病の予防を目的とした医療行為であり、既に発症した病気の治療費ではないため対象外と明確に位置づけられています。
税法上、医療費控除の適用範囲は所得税法施行令第207条において「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」として規定されており、予防的な処置は対象に含まれないと解釈されています。
そのため、予防接種だけでなく、健康診断や人間ドックといった予防を目的とした検査費用も、基本的には控除の対象外とされています。こうした費用は、個人の健康管理の一環として任意で行われるものと位置づけられているため、税制上の支援対象にはなりにくいのが現状です。
このように、医療費控除制度は、すでに発症している病気やけがの治療に伴う経済的負担を軽減することを目的としています。予防を目的とした支出については制度の対象外とする考え方が基本にあり、それが税法上のルールとして反映されているのです。
医療費控除の対象となる費用の範囲と条件
医療費控除とは、1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に一定額以上の医療費を支払った場合に、所得税の一部が軽減される制度です。対象となるのは、納税者本人だけでなく、生計をともにする配偶者や親族のために支払った医療費も含まれます。
医療費控除の適用には条件があります。具体的には、その年に支払った医療費が10万円を超える場合(総所得金額等が200万円未満の方は、その5%を超えた部分)に限り、控除を受けることができます。
控除の対象となる費用の例には、以下のようなものが含まれます。
- 医師または歯科医師による診療や治療にかかった費用
- 処方された医薬品の購入費用
- 入院にともなう費用(室料や食事代などを含む場合もあり)
- 通院に必要な交通費(原則として公共交通機関の利用に限る)
一方で、医療費のうち保険金や高額療養費などで補填される金額については、医療費控除の対象から差し引く必要があります。例えば、医療保険からの給付金や労災保険の支給などが該当します。
医療費控除の計算式は「支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額-10万円(または総所得金額等の5%)=控除額」となり、控除額の上限は200万円です。
例:40万円(医療費の合計)- 10万円(保険金など)- 10万円(自己負担の基準額)= 20万円(医療費控除の対象)
また、確定申告で医療費控除を申請する際には、「医療費控除の明細書」の提出が必要です。領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務があるので、捨てずに保管しておくようにしましょう。
この制度を活用することで、医療にかかった費用の一部が実質的に軽減される可能性があります。年末の整理や確定申告の準備にあたって、条件や対象範囲を事前に確認しておくと安心です。
セルフメディケーション税制でのインフルエンザ予防接種の役割
セルフメディケーション税制では、OTC医薬品の購入費用について所得控除を受けるために、一定の健康管理を実践していることが条件とされています。インフルエンザ予防接種は、この「健康管理の取り組み」の一例として位置づけられており、制度を利用する際の要件を満たす手段のひとつとなります。
通常の医療費控除とは異なる独自の要件と利点を持つこの制度について、詳しく見ていきましょう。
セルフメディケーション税制の概要と利用条件
セルフメディケーション税制は、健康維持や病気の予防に取り組む人を対象に設けられた、医療費控除の特例制度です。対象となるOTC医薬品(市販薬)を年間で12,000円を超えて購入した場合、その超過分の金額について、最大88,000円までを所得から差し引くことができます。
この制度の目的は、国民の健康寿命延伸と医療費抑制を両立させることにあります。従来の医療費控除は、年間10万円以上の医療費負担がある方でなければ適用されませんでしたが、セルフメディケーション税制では、より軽度な医療ニーズや予防的な取組みにも対応できるようになっています。特に日常的に市販薬を利用する方にとっては、比較的利用しやすい仕組みと言えるでしょう。
制度の利用には、単に医薬品を購入するだけでなく、次のような「健康管理の取組み」を行っていることが条件となっています。
- 保険者が実施する健康診査(健康保険組合など)
- 市区町村が行う住民健診
- 定期予防接種やインフルエンザ予防接種
- 勤務先での定期健康診断
- 特定健康診査(メタボ健診)
- がん検診(胃がん・乳がん・大腸がんなど)
いずれかの取組みを、その年中に実施していることが確認できれば、制度を活用するための要件を満たすことになります。
注意点として、セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除との選択制であることです。同じ年に両方を適用することはできず、どちらか一方のみを選択して申告する必要があります。一度申告すると後から変更はできないため、どちらの控除を利用するかは慎重に検討することが大切です。
この制度は、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの期間限定で実施されています。
参照元:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について|厚生労働省
インフルエンザ予防接種が要件となる「一定の取組」
セルフメディケーション税制を利用するには、申告者本人が「健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取組」を行っていることが前提条件となります。これは、税制の利用を通じて、日常的な健康管理の実践を促すことを目的とした要件です。
この「一定の取組」のひとつとして、インフルエンザの予防接種が明確に認められていますが、予防接種自体にかかった費用は医療費控除やセルフメディケーション税制の控除対象とはなりません。
ただし、インフルエンザ予防接種を受けたことを証明する領収書や接種証明書は、制度利用の要件を満たす証拠として重要です。これらの書類は、確定申告時の提出は必要ありませんが、税務署から確認を求められた際に提示できるよう、5年間の保管が義務付けられています。
制度を正しく活用するためにも、対象となる取組内容や必要な書類の扱いについて、あらかじめ確認し、適切に管理しておくことが大切です。
対象となるOTC医薬品の種類と識別方法
セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品には、大きく分けて2つの種類があります。
1つは、もともと医療用として使用されていた医薬品が一般用に転用されたスイッチOTC医薬品。もう1つは、制度改正によって対象に加わった非スイッチOTC医薬品です。
令和4年の制度改正以降は、以下のような成分や用途の医薬品が新たに対象となりました。
- 外用の鎮痛・消炎薬
- 解熱鎮痛薬
- 咳を鎮める薬(鎮咳薬)や痰を出しやすくする薬(去痰薬)
- 総合感冒薬(いわゆるかぜ薬)
- 鼻炎用の点鼻薬や内服薬
- 一部の抗ヒスタミン成分を含む製品
対象医薬品の識別方法として、一般社団法人日本OTC医薬品情報研究会が制定する共通識別マークがパッケージに表示されているものがあります。ただし、このマークの表示は義務ではないため、マークがない場合もあります。
薬局やドラッグストアでは、レシートに対象商品である旨が記載されることが多く、店舗によってはプライスカードで表示している場合もあります。商品パッケージだけでは判別しづらい場合もあるため、分からないときは薬局のスタッフに確認しましょう。
インフルエンザ流行時期に使われる市販薬の中では、アセトアミノフェンやイブプロフェンなどの成分を含む解熱鎮痛薬、総合感冒薬、咳止め薬の一部も、条件を満たせば対象となる場合があります。実際に購入する際は、厚生労働省が公表している最新の対象品目一覧を確認すると確実です。最新情報は、厚生労働省の公式サイトなどで確認できます。
医療費控除とセルフメディケーション税制の選択方法
医療費の負担を少しでも軽くしたいと考えたとき、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」のどちらを利用するべきか迷う方も多いのではないでしょうか。これらは併用できない選択制の制度であり、どちらか一方のみを適用する必要があります。
実は、年間の支出額や家族構成、医療の受け方によって、どちらの制度が適しているかは変わってきます。状況に応じた選択をすることで、結果的に節税につながることもあります。
それぞれの制度の特徴を知ったうえで、ご自身のケースに合った申告方法を選ぶことが大切です。ここでは、制度の違いや活用時のポイントについてわかりやすく解説していきます。
2つの制度の違いと選択時の注意点
医療費控除とセルフメディケーション税制は、対象となる費用の範囲や控除を受けるための条件が大きく異なります。
医療費控除は、本人や家族のために支払った年間の医療費が10万円を超えた場合に適用でき、控除額は最高200万円までとされています。一方、セルフメディケーション税制は、対象となるOTC医薬品の購入額が年間12,000円を超えた場合に適用でき、控除の上限は88,000円です。
これらの制度は併用できないため、同じ年に両方を使うことはできません。セルフメディケーション税制を選択した場合、他の医療費が10万円を超えていても医療費控除は受けられません。また、確定申告書を提出した後に制度を変更することも、更正の請求や修正申告では認められていないため、申告時には十分な確認が必要です。
重要な相違点として、セルフメディケーション税制では申告者本人が健康診断や予防接種などの「一定の取組」を行っていることが必須条件となります。さらに、対象となる医薬品も異なるため、同じOTC医薬品でも制度によって対象・非対象が分かれる場合があることに注意が必要です。
支出額や家族構成による有利な制度の見極め方
医療費控除とセルフメディケーション税制を比較する際には、控除額の差を基準に判断するのが基本的な考え方です。医療費控除では「年間の医療費合計から10万円を差し引いた金額」、セルフメディケーション税制では「対象OTC医薬品の購入額から12,000円を差し引いた金額」が、それぞれ控除額となります。
また、家族構成によって医療費が誰にどれだけかかっているかという分散状況が異なるため、世帯全体で支出を集計して比較検討することが大切です。個人単位で見るよりも、家族分を合算して計算することで、より正確に判断できるケースもあります。
具体的な選択の目安としては、以下のようなケースが参考になります。
年間の医療費が10万円未満の場合
医療費控除の適用条件を満たさないため、セルフメディケーション税制のみが選択肢となります。
年間の医療費が10万円以上188,000円未満の場合
実際の控除額を計算し、どちらの制度がより控除効果が高いか比較することが推奨されます。
年間の医療費が188,000円を超える場合
控除額の計算上、医療費控除の方が控除幅が大きくなる傾向があります。
家族の人数が多い世帯では、風邪薬や鎮痛薬など対象医薬品の購入頻度が自然と増える傾向があるため、セルフメディケーション税制の条件を満たしやすくなる可能性があります。一方で、慢性的な治療が必要な家族がいる世帯では、年間を通じた医療費が高額になることも多く、医療費控除が適しているとされる場合もあります。
なお、申告者の所得税率(課税所得の金額)も控除の効果に影響します。控除額が同じでも、税率が高い方が節税効果が大きくなるため、制度選択の際にはこの点も考慮しておくとよいでしょう。
日本一般用医薬品連合会では、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらがお得になるかを計算できるシステムがあるので、参考にしてください。
節税効果を高める申告のコツ
控除の恩恵を最大限に受けるためには、家族の医療費や対象OTC医薬品の購入費を適切に集計・整理することが効果的です。生計を同じくする家族であれば、所得税率が高い人がまとめて申告することで、税額控除のインパクトが大きくなるケースもあります。
また、対象医薬品の年間購入額が一定額(12,000円)を超えることが適用条件となるセルフメディケーション税制では、年末近くに対象医薬品をまとめて購入することで、下限額を超えやすくなります。
加えて、健康診断や予防接種などの「一定の取組」を計画的に受けることも、セルフメディケーション税制の要件を満たす上で重要です。年度内に一度でも受けていれば申告対象となるため、受診時期を意識することがポイントになります。
対象医薬品を購入する際は、必ずレシートを保管し、パッケージや明細に識別マークや対象表記があるかを確認する習慣を持ちましょう。また、翌年以降の申告に向けて、毎年どちらの制度がより有利かを検討することも大切です。家族の医療費や医薬品の購入状況に応じて制度を選び直すことで、長期的な節税につながる可能性があります。
確定申告での医療費控除手続きの流れ
医療費控除の申告を検討しているものの、「具体的にどのように進めればいいのか分からない」と不安を感じる方も少なくありません。申告書の作成から提出までの流れをあらかじめ把握しておくことで、スムーズに対応しやすくなります。
確定申告の受付期間は、例年2月17日から3月17日頃までの約1か月間です。この期間内に、必要書類の準備や申告方法の選択、記入手続きなどを行う必要があります。
効率的に進めるためには、あらかじめ医療費やOTC医薬品の購入記録、領収書、証明書類などを整理しておくことがポイントです。制度の違いを理解し、自分に合った申告方法を選ぶことで、よりスムーズな対応が可能になります。
申告期間と提出方法について
確定申告の受付期間(例年2月17日から3月17日頃までの約1か月間内)に申告書を提出する必要があります。ただし、還付申告の場合は1月1日から5年間申告が可能とされています。
申告書の提出方法には、次の3つの方法があります。
e-Tax(電子申告)
インターネットを利用して申告できる方法で、24時間利用可能です。税務署に足を運ぶ必要がなく、書類の郵送も不要です。マイナンバーカードを用いた認証か、ID・パスワード方式のいずれかでログインします。申告が受理された後、還付処理はおおむね3週間程度で完了するとされています。
郵送での提出
所轄の税務署へ郵送する方法です。申告期限日の消印が有効となるため、締切日直前の投函には注意が必要です。
税務署窓口へ持参
税務署の開庁時間内であれば、直接持参して提出することも可能です。ただし、混雑が予想される時期は待ち時間が発生する場合もあるため、余裕を持った来署が推奨されます。
初めて確定申告を行う場合は、必要書類の準備に2週間程度を見込んでおくと安心です。特にe-Taxを利用する予定がある場合、マイナンバーカードの取得には1か月以上かかるケースもあるため、早めに申告しましょう。
また、e-Taxの利用には、利用者識別番号の取得や、必要に応じて開始届出書の提出が必要です。事前準備をしっかり行うことで、スムーズに申告が進められるようになります。
参照元:【確定申告・還付申告】|国税庁
医療費控除に必要な書類と記入方法
医療費控除を申告する際には、「医療費控除の明細書」の提出が必須となります。この明細書には、医療を受けた人の氏名、医療機関や薬局の名称、医療費の内容や金額、保険などで補填された金額などを記載する必要があります。領収書の添付は不要ですが、明細書の記入内容確認のため5年間の自宅保管が義務付けられています。
明細書で算出した控除額は、確定申告書の第一表「所得から差し引かれる金額」欄の㉗ 医療費控除に記入します。健康保険組合などから送付される「医療費通知(医療費のお知らせ)」を持っている場合は、一定の要件を満たせば明細書の代替として提出することが可能です。ただし、記載情報が不足している場合は、不足分について明細書を別途作成する必要があります。
申告書の作成を効率よく進めるためには、国税庁が提供している「医療費集計フォーム」の活用がおすすめです。表計算ソフトで医療費を整理したうえで、確定申告書等作成コーナーに読み込ませることができるため、手作業の負担を軽減できます。また、マイナポータルと連携することで、医療費通知情報を自動で取り込む機能も利用可能です。
セルフメディケーション税制申告時の準備書類
セルフメディケーション税制を申告する場合は、専用の「セルフメディケーション税制の明細書」が必要となります。この明細書には、医薬品の購入先(支払先)の名称、購入した医薬品名、支払額のほか、制度の要件である「一定の取組」に関する情報として、取組の種類と、それを証明する書類の発行者名を記載する必要があります。
「一定の取組」とは、申告者本人が健康管理の一環として行った取り組みのことで、次のような書類が証明書類として認められています。
- 健康診断やがん検診の結果通知書
- 定期健診や予防接種の領収書や接種証明書
- 特定健康診査や人間ドックの結果通知など
令和3年分(2021年分)以降の申告については、これらの書類の提出は原則不要とされています。ただし、税務署から確認を求められた際に提示できるよう、5年間は自宅で保管しておく必要があります。
OTC医薬品の購入記録を整理する際には、対象商品であるかどうかを確認しましょう。パッケージやレシートに、セルフメディケーション税制対象商品であることを示す識別マークや「対象商品」の表記がある場合があります。これはメーカーや販売店によって異なるため、購入時に確認しておくと安心です。
また、明細書を効率的に作成するためには、支払先ごとに購入した医薬品をまとめて整理する方法がおすすめです。必要項目を簡潔に記録しておくことで、後から申告書類を作成する際の手間を軽減できます。
